
皆さんこんにちは、古文科の加藤です。
古文学習の必須でもある「古文単語」。この学習には皆さん向き合っていると思います。
「学校や予備校の単語テストが大変」という方もいるかもしれませんね。「現代語で今でも使うのにも関わらず、何で意味が違うのか」など、悩む人もいらっしゃるでしょう。
実は、古文単語はコツコツやっていけば意味はしっかり入っていきます。その導入として、今回は古文単語学習を効果的に行う方法を紹介します。
目次
古文単語の学習にも「効果的に進めていく方法」はある
「この言葉は現在も使っているのですが、何故意味が違うのですか」という質問を頂くことは非常に多いです。
確かにその通りで、そのように感じるのも仕方ないとも言えます。これは言語変化の中で起こってしまう現象として仕方のないことで、言葉は生き物ですからある程度どの言語にも見られる現象だと思います。
(もちろん現代語と同じ意味で本文中に使用されている単語もあるので、注意が必要です。)
しかし、一見大変そうに見える単語学習も、効果的に進めていく方法はあります。具体的な学習法に移っていきましょう。
自分に合いそうな単語帳を選ぼう
書店で古文単語帳のコーナーにいくと、実に多様なものが売られていますよね。
自分の手になじんでいる、学習しやすい単語帳を使う
基本的には自分の手になじんでいる、学習しやすいと感じられるものを使用するとよいと思います。
「学校配布のもので単語テストの習慣が有る」「予備校で配ってくれたものが普段の授業と連動していて使いやすい」などであれば、あえて買い替える必要はないかな、と思います。
おすすめの古文単語帳
「古文の年間学習ロードマップ」の記事中でも、比較的多くの受験生が使用しているものを提示しました。
古文常識や和歌の修辞も収録されており、使いやすいと思いますよ。
古文単語の効果的な学習法①:単語が持つ「イメージ」の連鎖から複数ある語義を獲得する
その単語が持つ「イメージ」の連鎖から複数ある語義を獲得していく学習法です。
古文単語は1つの単語が4つくらい意味を持っているものもあるので、ストイックにひたすら覚えていくのは辛いですよね。
例えば「心もとなし」という単語であれば、以下のように授業では解説しています。
そんなときは、状態が完全に掴めていないことが多いから、
- 気がかりだし、不安だ
- 待ち遠しい、じれったい(早く事態が明らかになってほしいですよね)
- (そしてその対象が)ぼんやりしている、はっきりしない(から起こります)。
というようにイメージを連携させると覚えやすくなるから、試してみくださいと伝えています。
私は機械的な暗記が苦手な受験生だったので、ひたすらこのやり方を実践していました。
古文単語の効果的な学習法②:プラスマイナス双方の意味を持つ語は重点的に学習する
また、プラスマイナス双方の意味を持つ語は重点的に学習しましょう。
文脈上どちらの意味で取るかを選択肢中で選ばせる問題などもありますから、要注意です。
単語帳は「1冊しっかりやり切る」or「2冊併用」
「単語帳は1冊でよいか」というご質問も頂きます。
これは少し判断が悩ましいところですが、もう一冊用意しておくことで学習効果は上がると思います。
具体的なテキストとして1冊ご紹介します。

こちらは、難関大志望の方や、「読解も並行して勉強したい」という方にお勧めです。やや難易度は高いですが、取り組んだ成果は必ずでると思います。
古文単語帳の活用法、学習ペースについて
「どれくらのペースで単語は覚えたらいいの」「毎日50語ぐらいやっているけど、全然頭に入らない」。
このような相談は何度も聞きます。気持ちは分かります。「〜までやったら覚えられた」という確信は、中々感じにくいのではとも思っています。
「毎日50個の単語やっているのに、全然出来るようにならない、どうしたらいいですか」という問いには、私はこう答えるようにしています。
おそらくそれが実現できたのは毎日少しずつ、色んな場面で出会ったからでしょう。
未知の単語に出会ったら必ず調べ、痕跡を残す
日々の読解演習や短文中の単語、模試の復習など様々な場面で未知の単語に出会った時には必ず調べ、そして調べたあとをマーカーやテキストへの書き込みなどで残してください。
「単語帳の最初の方は覚えているのに、後半辺りから不安で」という悩みの解決の糸口になるかもしれません。
1ヶ月に100〜120語程度を目安に学習する
学習目安の単語数例を改めてまとめておきます。
もちろんどんどん学習を進める方がいいという方は、この限りではありません。自分の最適なペースを見つけてみてください。
あまり負荷を感じず、確実に覚えていくのが理想です。
- 1日に無理をしすぎず、詰め込み過ぎない。日々のルーティーン学習派なら1日に5~10語程度、週単位で学習量を調整したい場合は30~50語程度。
文脈確認のために、収録されている例文全体を読むこと。 - 月単位で換算すると100から120語程度
単語帳を簡易辞書として活用しよう、さらに辞書も併用しよう
ここからが重要です。より具体的に学習の仕方をお示しします。
知らない、不安な単語に出会ったら必ず単語帳・辞書で引く
学校や予備校、独学でで使っている読解用テキストに登場した、「知らない」「なんとなくは知っているけど少し不安」という単語に出会ったら、必ず単語帳で引いてください。
そして意味を調べた単語には単語帳にマーカーやチェックを入れ、読解教材の余白に単語と意味を書き込みましょう。
これで、「マーカーを引いて覚える」という視覚的暗記とともに、「書いて覚える」いう作業も同時に行われるわけです。
学校や予備校での先生の板書で紹介された単語でも、同じ作業をしてください
。
単語帳に未収録の単語は単語帳に書き足す
また、未収録の単語を見つけたら、付箋などを使って自分の単語帳に書き足してください。これで皆さんオリジナルの単語帳が完成していくわけです。
単語帳は、入試が終わってその中で出題された頻出語を収録していますよね。辞書と重要語の位置づけが違うこともそれなりにあります。
学習において既視感は大切ですし、チェックの数が増えると達成感も生まれます。
辞書のコラムも活用する
そして、辞書のコラムなども古文常識の宝庫ですから、是非活用してくださいね。
ただ、辞書でも重要度が低く、単語帳にも載っていないところまでの学習は難しいと思います。しかしそれがもし入試で問われたときは別のアプローチで得点を取りに行きます。それはまた読解法などの回で改めてご紹介致しましょう。
先ほどからお伝えしている辞書については、前回記事の中で1冊ご紹介させて頂いております。
これまでの内容を整理してみましょう。
- 単語帳を最初から読み書きを通じて行う
最もスタンダードな学習法だと思います。その際は、語源や例文などの確認も忘れずに - 単語帳を辞書代わりに活用する
読解問題、短文解釈などで不明なものが出てきたらチェック。その語を今度は辞書でも引いてみる - 単語帳に載っておらず、特に辞書の中で赤字や太字で示されているものは、付箋などで追加
これで収録単語数に対する不安解消にもなります
これで、「単語帳ではまだ後ろの方にあるのに、見たことがある」という実感が生まれます。
このように、2方面、3方面からの単語帳の活用が「繰り返しのその単語と出会い、意味が獲得できた」という結果に繋がるでしょう。
時期別の古文単語学習イメージ
最後に、古文単語の学習イメージを時期別に紹介します。
学習開始期:「基礎語」「重要語」から取り組む
単語学習は「年間を通じて行いたいこと」です。
「基礎語」「重要語」などと分類されているものを用いている場合はまずそこから取り組みましょう。
もちろん、未知の単語を調べることは後に行うことの先取りですから、取り組んでくださいね。
夏期以降~冬期前:難単語の習得まで目指す
夏以降本格的に過去問演習などに取り組む際には、「基礎語重要語は複数語義まで覚えている、難単語の習得まで目指そう」という意識でいてください。
「自分の志望校はどのレベルの難易度の単語力を要求しているのか」ということを意識しながら学習を進めることも大切です。
直前期:自分の単語帳を見直す
追い込みのこの時期では、過去問演習や様々な学習で忙しいでしょう。志望校の単語レベルチェックは述べましたが、ここでもう一度自分の単語帳を見直してみてください。
付箋部分の確認、チェックが多くついている語や、少し覚えにくさを感じたなどの最終チェックをしましょう。試験会場に持っていく心強い最高の教材となっていることを望みます。
古文単語は「学習すればするほど良い結果につながる」もの
さて、今回は「古文単語」の学習ということに特化をしてお話をしてました。語学を学ぶ中で、単語は文法と共に要となる部分です。
しかし、古文単語は獲得すればするほど読解も進みますし、知っていたはずなのに思い出せずに悔しい思いをしてしまう恐れもあるものです。ですから、「学習すればするほど良い結果につながる」と、肯定的に捉えて取り組んでみてください。
皆さんの古文学習がさらに実りの多いものになるよう、応援しています。

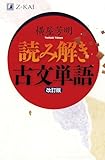





![[化学]過去問の使い方](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_150,h_150/https://www.educational-lounge.com/wp-content/uploads/2018/11/b4531233b250804f287b9a062c243f73_s-1-150x150.jpg)
![[化学]化学用語を覚えよう②](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_150,h_150/https://www.educational-lounge.com/wp-content/uploads/2018/11/0f49fd4d131affdcad5376a82b41c82b_s-150x150.jpg)






